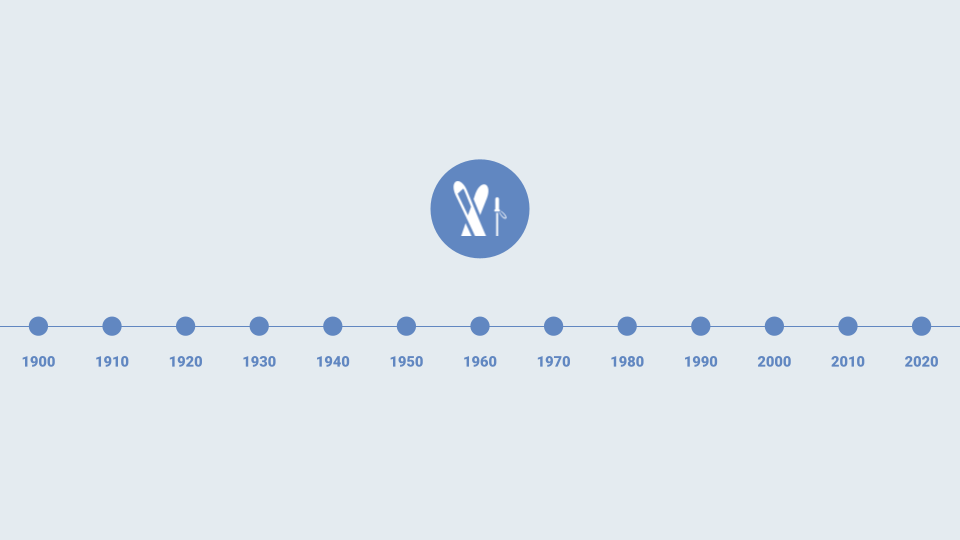日本におけるスキーの歴史や背景を追いながら、世代ごとにどのようなスキーブランド・スキーメーカーが登場してきたのかを見ていく。スキーの時代背景の変化と共に登場するスキーメーカーの遷移を通じて、その時代のスキー文化に想いを馳せたい。
以下では、スキーブランドおよびメーカーの創業年を年表形式でまとめた。ただし、創業年が必ずしもスキー板の製造開始年と一致するわけではなく、ここでは、各ブランドの創業年を基準に一覧化している。

1900年代初期:スキーの始まり
1900年代初頭は、スキーがスポーツとしての基盤を築き始めた時代である。当初スキーはヨーロッパの雪深い地域で移動手段として活用されていたが、この時代は次第に娯楽や競技の要素が加わり、今まではノルディックスキーとしての要素が強かったスキーが、アルペンスキーとしても進化していった時代でもある。1905年にはマチアス・ツダルスキーが初めてスラローム(トールラウフ)の原型となるアルペンスキー競技会を開催し、スポーツとしてのスキーに新たな方向性を示した。一方、日本では1911年、オーストリア・ハンガリー帝国のテオドール・エドラー・フォン・レルヒ少佐が1月12日に日本陸軍に対し本格的なスキー指導を行い、これが日本におけるスキー文化の端緒となった。(スキーの歴史)
この時期に立ち上がったスキーブランドは以下の通りだ:
1920年代~1940年代:スキーリゾートの基盤形成
日本におけるスキーの歴史を振り返ると、大正時代(1912年~1926年)中頃には、スキー滑走が全国的に知られるようになった。なだらかな山の斜面や丘陵地、城の坂道、川の土手など、さまざまな場所でスキーが楽しまれたが、昭和初期までは「スキー場」ではなく「スキー地」と呼ばれていたのが特徴的だ。この時代、文部省が毎年スキー普及のための講習会を開催したこともあり、鉄道を活用した都市部からのスキー・ツーリズムが盛んになり始めた。1924年には鉄道省が「スキーとスケート」を出版し、鉄道路線に沿った全国51か所の「スキー地」を紹介している。(スキー場の広まり)
スキーの普及とともに宿泊施設の整備も進み、スキーリゾートの基盤が築かれた。1920年代後半には鉄道の開通や不況の影響を受け、農家が現金収入を得るために民宿を本格化させた。特に細野地区(現在の八方)では、公式な民宿営業が始まり、日本の民宿文化の先駆けとなった。(民宿とは)1937年には志賀高原丸池に「志賀高原温泉ホテル」、妙高赤倉温泉には「赤倉観光ホテル」が建設されるなど、洋風ホテルがスキーリゾートの中核として次々と誕生。温泉地や農村を中心に、スキーリゾートの原型が形作られていった時代だ。
このようにスキーリゾートの基礎が整っていく中で、各国では以下のようなスキーブランドが誕生してきた。
| 名前 | 創業年 | 創業地 | 創業者 | 公式サイト | 歴史 |
|---|---|---|---|---|---|
| Völkl | 1923年 | ドイツ・シュトラウビング | Franz Völkl | 公式サイト | 歴史 |
| Bluemoris | 1923年 | 日本・青森 | 鈴木大観ら *株式会社青森スキー製作所設立時 | 公式サイト | 歴史 |
| Fischer | 1924年 | オーストリア・リート | Josef Fischer Sr. | 公式サイト | 歴史 |
| Kästle | 1924年 | オーストリア・ホーエネムス | Anton Kästle | 公式サイト | 歴史 |
| Stöckli | 1935年 | スイス・ウォールヒューゼン | Josef Stöckli | 公式サイト | 歴史 |
| Nordica | 1939年 | イタリア・トレヴィーゾ | Adriano and Oddone Vaccari | 公式サイト | 歴史 |
| Blizzard | 1945年 | オーストリア・ミッタージル | Anton "Toni" Arnsteiner | 公式サイト | 歴史 |
| Elan | 1945年 | スロベニア | Rudi Finžgarや他9名 | 公式サイト | 歴史 |
| Salomon | 1947年 | フランス・アヌシー | François Salomon | 公式サイト | 歴史 |
| Head | 1947年 | アメリカ | Howard Head | 公式サイト | 歴史 |
1950年代~1960年代:スキー場の広まり
1950年頃からはスキーリフトを伴った本格的なスキー場開発が開始されるようになり、馴染み深い「スキー場」の形が出来上がってくる。1955年ごろは高度経済成長期に入り、住宅や自動車・カラーテレビ・電話などの普及も進み、生活基盤が整っていった時代にある。1961年には「レジャー」が流行語となり、各地の観光地への旅行客が増加し,スキーも冬季のレジャーとして注目が集まった時期であり、レジャーにお金を使えるようになってスキーも人気が高まってくるようになった。(スキーの広まり)
| 名前 | 創業年 | 創業地 | 創業者 | 公式サイト | 歴史 |
|---|---|---|---|---|---|
| スワロースキー | 1950年 | 日本・飯山 | - | 公式サイト | 歴史 |
| Atomic | 1955年 | オーストリア・アルプス | Alois Rohrmoser | 公式サイト | 歴史 |
| Hart | 1955~2022? | アメリカ・ミネソタ州 | Hartvig “Hart” Holmberg | 公式サイト | - |
| Scott | 1958年 | アメリカ・アイダホ州・サンバレー | Ed Scott | 公式サイト | 歴史 |
| K2 | 1962年 | アメリカ・ワシントン州 | Bill Kirschner | 公式サイト | 歴史 |
| Black Diamond | 1965年 | アメリカ | Yvon Chouinard *「Chouinard Equipment」設立時 | 公式サイト | 歴史 |
| Dynastar | 1963年 | フランス・シャモニー | - | 公式サイト | 歴史 |
1970年代~1990年代:スキー観光の発展
日本のスキー観光が最も隆盛を極めたのは、バブル景気に伴うこの時期である。1980年代後半から1990年代にかけて、スキー人口は1800万人に達しピークを迎えた。大都市から積雪地帯への高速交通網が整備される中、各種キャンペーンやコンテンツがブームを後押しした。1987年に公開された原田知世主演の東宝映画「私をスキーに連れて行って」が大ヒットし、スキー人気に拍車をかけたほか、1990年の「JRSKISKI」キャンペーンもスキー場開発のブームを加速させた。(スキーの広まり)
この時代の国内のスキー生産はどのような状況だったのか。
赤羽(1989)によると、1970年頃にはカザマ、西沢、小賀坂、ヤマハの4社が国内生産の約6割を占め、それに続く形でハセガワ、美津濃(ミズノ)、アジアなどが存在していた。しかし、1971年のドルショックや1973年の変動相場制への移行、第1次オイルショックの影響により、スキー生産量は急激に落ち込む。1976年頃に一時的な回復を見せるものの、1977年以降は輸出の急減と輸入スキーの増加が顕著となり、国内生産は次第に衰退していった。特に円高傾向が進む中、輸出は不振に陥り、逆に海外産スキーの国内市場への流入が進行。これにより国内需要は輸入品に押され、国内スキー生産は縮小の一途をたどる。
以下に、赤羽(1989)の図表を引用する:
赤羽孝之. (1989). 新潟県上越地方におけるスキー工業ーーある地場産業の崩壊一一. 歴史地理学, 146, 20. / p22の図1を引用
また、赤羽(1989)によれば、1989年時点において日本に流通していたスキーは以下をあげている。
1989年時点の国内の主要スキーメーカー:
- カザマスキー(新潟県)
- ハガスキー(北海道)
- 青森スキー(青森県)
- ミタケスキー(岩手県)
- 小賀坂スキー(長野県)
- スワロースキー(長野県)
- 西沢(長野県)
- ヤマハ(静岡県)
- 美津濃(大阪府)
1989年時点の輸入スキーと取り扱い商社:
- ヘッド:大沢商会
- フィッシャー:兼松スポーツ
- アトミック:アシックス
- K2:K2ジャパン
- エラン:第一商会
- ブリザード:丸紅スポーツ
- ロシニョール:三井物産スポーツ
- グナイスル:リーベルマン
- ケスレー:日本ノルディカ
これらの商社や販売会社が、フランス、オーストリア、アメリカ、ユーゴスラビアなどからスキーを輸入し国内で販売していた。スキーの需要がピークに達する一方で、国内生産の縮小と輸入品の増加が進む中、日本のスキー市場は徐々にグローバルな競争の波に飲み込まれていく。
この時代、生まれたブランドは以下の通り。
| 名前 | 創業年 | 創業地 | 創業者 | 公式サイト | 歴史 |
|---|---|---|---|---|---|
| Extrem | 1981年 | スウェーデン・エステルスンド | Patrik Söderlund, Stefan Cederberg | 公式サイト | 歴史 |
| Lib Tech | 1983年 | アメリカ | Mike Olson, Pete Saari | 公式サイト | 歴史 |
| Line Skis | 1995年 | アメリカ | Jason Levinthal | 公式サイト | 歴史 |
2000年〜2020年:新たなスキーカルチャーの台頭
一時期盛り上がりを見せたスキーツーリズムも、バブル崩壊を機に停滞期に突入し、スキー人口は減少の一途をたどった。1998年の長野オリンピックで日本人選手がジャンプやモーグルで活躍し、一時的にスキーとスノーボードの人口が増加するも、その後は再び低迷が続く。経済状況の悪化により、レジャーへの支出を控える人も増えた。
この時代に2000年代には新しいスキーのスタイルが登場する。それがフリースキーやフリーライドスキーといった新たなカルチャーである。
1990年代のスキー場は大きな変革期を迎えていた。その背景にはスノーボードの台頭があり、従来のスキー文化に挑戦する形で新たな活気をもたらした。90年代初頭には音楽、ファッション、ダンスを巻き込んだ「ニュースクールムーブメント」が起こり、スノーボードもこのムーブメントの中で発展。これにより、スキーリゾートにはハーフパイプやテレインパークが次々と設置されるようになった。(スノーボードの歴史)
しかし、こうした施設の利用は当初スノーボーダーが中心であり、スキーヤーの間では少し距離があった。その状況を変えたのが、パークで自由な滑走を展開するスキーヤーたちである。特に、ツインチップスキー(板の前後が反り上がり、後ろ向きでも滑りやすい仕様)の発明は、「フリースキー」の知名度を急速に高めた。(フリースキーの歴史)
一方で、「フリーライド」文化の台頭も重要な流れである。1930年代から1940年代にかけてフランス・シャモニーでエミール・アレが急斜面での滑走を披露するなど、非圧雪の地形でスキー表現をすることは早くから存在していた。1970年代には、ほとんどのプロがスキーレーサーになることを目指すかプロモーグルツアーで回るというキャリアを送る中、過酷な斜面で芸術的なフリーライディング表現を行なうスキーヤーも出始め、1988年『Blizzard of Aahhh』に代表される様々なムービーをきっかけに「フリーライド」のスタイルがメディアを通じて広がりを見せる。1991年にはアラスカ州バルディーズで「 the 1st World Extreme Ski Championships」が開催され、現在では「フリーライドワールドツアー(Freeride World Tour)」が開かれるように。フリーライドカルチャーが日本でも広まってきたのがこの頃と言って良いのかもしれない。(フリーライドの歴史)
さらに2000年代に入ると、日本のスキーリゾート、特にニセコが外国人観光客の人気を集めるようになった。オーストラリアを中心とした海外のスキーヤーたちがニセコのパウダースノーに魅了され、「JAPOW(Japan Powder)」として世界的に注目されるようになっていく
このように、2000年代はパウダースノーの魅力やフリースキー・フリーライドスキーといった新たなスキー文化が成長を遂げた時代であり、スキーブランドを見てみても、この時代に一気にフリースキーやフリーライドスキーを中心とするブランドも生まれてきていることがわかる。
| 名前 | 創業年 | 創業地 | 創業者・団体 | 公式サイト | 歴史 |
|---|---|---|---|---|---|
| ID one | 2000年 | 日本 | 株式会社マテリアルスポーツ | 公式サイト | 歴史 |
| Armada | 2002年 | アメリカ | JP Auclair, Tanner Hall 他 | 公式サイト | 歴史 |
| ZAG | 2002年 | フランス | Stéphane Radiguet | 公式サイト | 歴史 |
| 4FRNT | 2002年 | アメリカ | Matt Sterbenz | 公式サイト | 歴史 |
| Field Earth | 2003年 | 日本 | 本村勝伯 | 公式サイト | 歴史 |
| Vector Glide | 2003年 | 日本 | 秋庭将之 | 公式サイト | 歴史 |
| DPS | 2005年 | アメリカ | Stephan Drake, Peter Turner | 公式サイト | 歴史 |
| Icelantic | 2005年 | アメリカ | Ben Anderson | 公式サイト | 歴史 |
| Blackcrows | 2006年 | フランス | Camille Jaccoux, Bruno Compagnet | 公式サイト | 歴史 |
| Faction Skis | 2006年 | スイス・ヴェルビエ | Tony McWilliam | 公式サイト | 歴史 |
| TONES SKI | 2006年 | 日本・白馬 | 舎川朋弘 | 公式サイト | 歴史 |
| Majesty | 2007年 | ポーランド | Janusz Borowiec | 公式サイト | 歴史 |
| RMU | 2008年 | アメリカ・コロラド州 | Mike Waesche | 公式サイト | 歴史 |
| Blastrack | 2011年 | 日本・長野 | 小賀坂スキー製作所 | 公式サイト | 歴史 |
| Wapan Skis | 2017年 | 日本 | ReMo株式会社 | 公式サイト | 歴史 |
2020年以降〜
2020年以降、スキー産業は新型コロナウイルスの影響により、パンデミックによるリゾートの一時的な閉鎖や移動制限により低迷し大きな変化を経験した。環境問題への対応も引き続き産業全体が直面する重要な課題であり、スキーメーカーの中でもFactionやIcelanticのB Corp認証といった環境や社会に対してのアクションを起こしているメーカーも出てきている。
さらにSNS等のメディアもスキーの魅力を新たな世代に伝える重要な役割を果たしていくだろう。InstagramやYouTubeといったプラットフォームを活用し、映像がスキーヤー同士で共有されることで、スキー文化がグローバルに広がっていると推測される。
日本国内では、2024年時点で引き続きニセコや白馬といったスキーリゾートが注目され、リゾート開発がどんどんと進んでいる。コロナ禍の影響が緩和されてスキーヤーのインバウンド客も客足が戻り、「JAPOW(Japan Powder)」というブランドが世界的に浸透しつつあるようだ。この動きにより、日本のスキーリゾートが地域経済の再生に貢献する重要な役割を担うかもしれない。
2024年時点のリサーチ時点で出てきているブランドを下記に上げたい。
| 名前 | 創業年 | 創業地 | 創業者 | 公式サイト | ストーリー |
|---|---|---|---|---|---|
| Season Eqpt | 2020年 | アメリカ・オレゴン州 | Eric Pollard, Austin Smith | 公式サイト | ストーリー |
| Van Deer | 2022年 | オーストリア | Marcel Hirscher | 公式サイト | ストーリー |
| Simply. | 2023年 | スイス・ヴェルビエ | Laurent De Martin | 公式サイト | ストーリー |
ここから、スキーメーカーはどのように進化していくのだろうか。環境問題へのさらなる対応や技術革新、そして新しいライフスタイルや価値観に応じた製品の開発が求められる中、次の時代に向けてどのような形を描き出していくのか。未来のゲレンデでどんなスキー文化が展開されるのか今後も注目していきたい。
参照:
赤羽孝之. (1989). 新潟県上越地方におけるスキー工業ーーある地場産業の崩壊一一. 歴史地理学, 146, 20. Retrieved from http://hist-geo.jp/img/archive/146_020.pdf