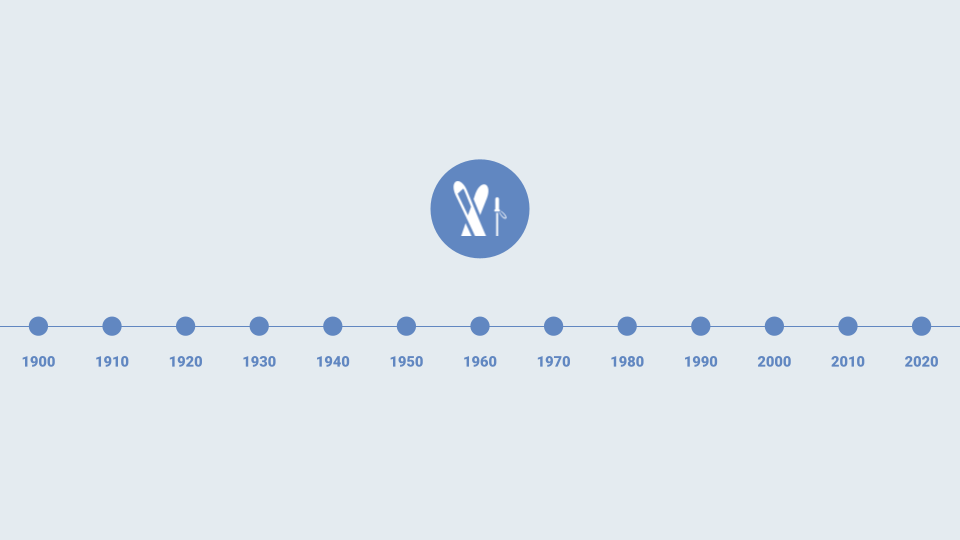狩猟や移動、信仰のために山を登る行為は、かつて人々にとっては生存のための行為だった。時代とともに、山登りは人々にとって探究、挑戦、楽しみのためと異なる意味を持ち始めた。西洋と日本、それぞれに異なるアプローチをたどりながら、人と山の深い関わりを探る。
ヨーロッパの登山思想:恐怖から探求へ
かつてヨーロッパの山々は、単なる自然の風景ではなかった。むしろ、それは悪魔や魔女が棲むと恐れられ、人が足を踏み入れてはならない領域とされていた。18世紀末までは、山岳は人間の手の届かない、忌むべき場所であり、探求や冒険の対象ではなかった。それにこの時代のキリスト教による支配下では、宗教に都合の悪い探究は容赦無く弾圧され、素直な好奇心や科学的探求は抑圧されてきた。
イタリアの医師ピエトロは1316年に「地球は丸い」と唱えて告発されたり、ガリレオは、地動説を支持したことで異端審問にかけられていた時代だ。

この認識が揺らぎ始めたのは、17世紀の宗教改革と科学革命が到来した頃。大航海時代の時代とともに共に変わり始める。大航海時代を経てヨーロッパは新たな知識や異国の品々に触れる機会を得た。こうして珍しい品々をコレクションする人々が増え、「博物学」のブームが起こり、自然への関心が急速に高まっていく。
17世紀には数学や物理学が急速に進展し、18世紀になると博物学が花開いた。自然そのものへの興味が深まる中で、かつては恐怖の対象だった「山」も、探求と美の対象としてその価値を見出されていったのだ。

ヨーロッパの山々はこうして、恐れの象徴から、知識と美を求める探求者たちの舞台へと姿を変えていった。
アルプスブーム、アルピニズム、近代登山の幕開け
こうして好奇心の目が山に向けられると、調査や研究のために山々へ足を踏み入れる人々が現れ、研究だけでなく、詩人や哲学者たちも山に入りその美しさを称賛するようになった。これにより、ヨーロッパではアルプスブームが起こり、スイスを観光地として訪れる人々が増加していった。
18世紀後半から19世紀にかけてはかつて恐怖の対象だった山々が、登山の登頂目標としても注目されるようになる。1786年にはモン・ブランの初登頂が達成され、これをきっかけにアルプスの山々が次々の登頂されていく。

モンブランの初登頂を達成したジャック・バルマ - パブリックドメイン
産業革命後の豊かになったイギリスでも登山家たちがアルプスの未踏峰に挑戦する動きが活発化した。1857年には世界初の山岳会「アルパイン・クラブ」がイギリスで設立。登山は単なる探求やレジャーの場に留まらず、スポーツとしての顔も持つようになっていく。このアルピニズムの精神は、やがて日本にも伝わるが、その前に日本の山登りの歴史も振り返ってみたい。
山岳信仰・修行としての登山
ヨーロッパの登山は中世ごろから始まったのに対し、日本の山登り・登山の起源は縄文時代まで遡る。人々は山に対して畏敬の念を抱き、自然と神とのつながりを見出してきた。特に稲作を中心とする農耕時代には、大切な水は山から流れてくるため、豊かな収穫を祈るという意味でも山の神が田の神とされた山からの水は水害を引き起こす脅威でもあった。感謝の念と畏怖の念が山岳信仰を発生させた。
山は修行の場としても重要な役割を果たした。修験道や仏教など山での修行を通じて悟りを開く僧たちが現れ、日本における山岳信仰はますます強固なものとなっていった。

江戸時代後期になっても登拝登山は行われてはいたものの、山岳信仰は次第に「物見遊山」としての登山へと変わり、山を訪れる人々の目的も多様化していく。そして明治時代、開国後に外国人登山家が日本の山々を訪れ、日本の山々にも先述したようなスポーツとしての「登山」文化が流入していくこととなる。
日本での近代登山の始まり
日本における登山は、古来より信仰や修験道の一環として行われてきた。しかし、近代登山の概念が本格的に導入されたのは、19世紀後半、英国の登山家ウォルター・ウェストンの登場が大きなきっかけとなった。1888年、ウェストンが日本に足を踏み入れ、日本アルプスの山々に挑んだ。彼の著書『日本アルプス―登山と探検』が1896年にロンドンで出版されると、これは日本の登山愛好家たちに多大な影響を与えることになり、近代登山の基盤を形成した。1905年には日本初の山岳会も形成され、近代的な登山(つまり従来の信仰登山とは違う、好奇心、冒険心に基づくスポーツ的要素を含む登山)が日本でも幕を開けることとなる。
1911年にはレルヒ少佐がスキー技術を伝授することでスキー登山が日本に導入され、これにより冬の山岳活動は新たなフェーズを迎え、雪山登山の可能性が広がる。スキー技術の伝来によって積雪期登山の幅が広がっていった。

1920年代には、日本人によるアルプス登山が本格化し、国内外の山々で挑戦が繰り広げられた。1921年、日高信六郎がモン・ブラン(4,807m)の日本人初登頂を達成。同年9月には、槇有恒がアイガー東山稜を初登攀し、アルプスの登山史に新たなページを刻み、日本の登山者にも大きな影響を与えた。

1930年代に入ると、『山と渓谷』をはじめとする山岳雑誌も創刊されるようになり全国的に登山熱が高まるようになった。
戦後から現代の登山ブーム
第二次世界大戦後、登山は日本で一大ブームを迎える。特に1960年代のマナスル登頂を機に登山は再び注目され、大衆の間で広まっていく。そして、1990年代に入ると中高年層の登山熱が高まり、「日本百名山ブーム」が到来する。
山に登るという行為は、時代や文化によって多様な意味を帯びてきた。アルピニズムの冒険精神や宗教的修行から、現代の健康志向に至るまで、人々は山を登ることでさまざまな意義を見出してきた。これから先、山を登る行為がどのような新たな価値や意味を生み出すのか、未来への問いは続く。
参照:
国立登山研修所. 登山の歴史と文学
小泉 武栄(2001). 登山の誕生: 人はなぜ山に登るようになったのか 中公新書